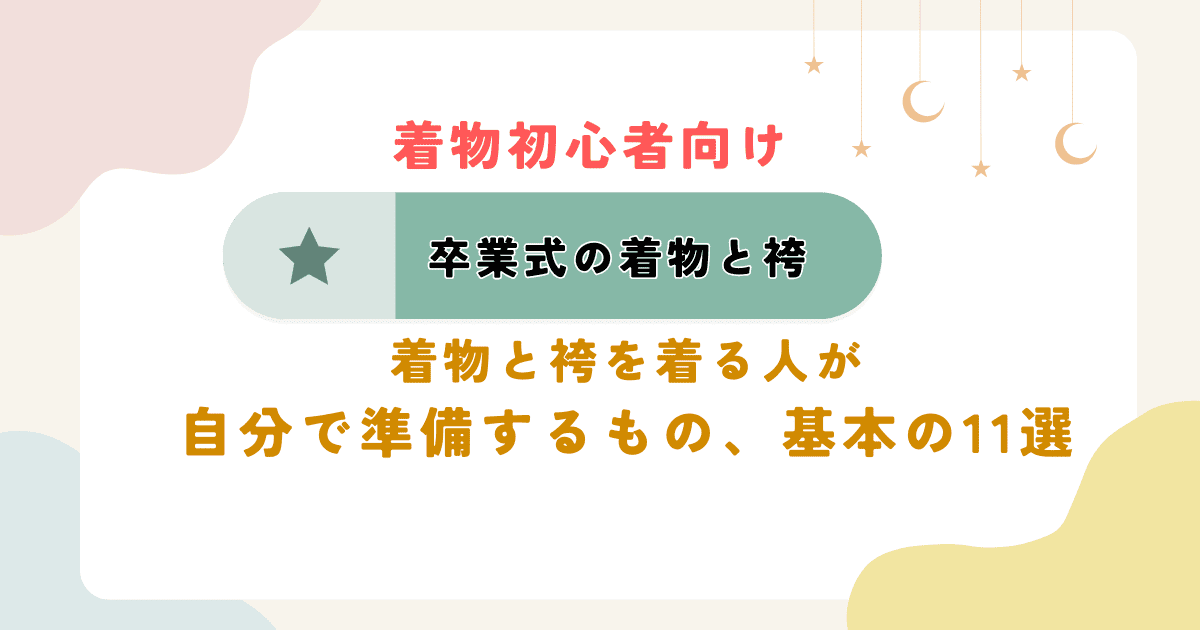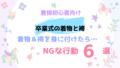こんにちは。wakabaです。
卒業式に着物&袴を着ると決めたら……着物と袴を準備しますよね。
でも、それだけでOK……?

……ではなく、着物&袴を買う人も、レンタルする人も、他にも必要なものがありますよ。
結構いろいろあるので卒業式の直前に、一気に全部そろえようと思ったら大変です。徐々にそろえていったほうがいいのではないかと思います。
そこで今回は、卒業式の当日までに必要なものをご紹介します。
この記事はこんな人におすすめです。
・着物&袴を着るときに、必要なものを知りたい人
・着物&袴を買う予定の人
・着物&袴をレンタルする予定の人
どんなものが必要なのかを知って、計画的に準備を進めていってもらえたらと思います。
では、始めましょう!
必要なものは人によって違います
これから着物&袴を着るときに必要なものを紹介していきますが、これはあくまでも基本的なものです。卒業式に着物&袴を着るすべての人に必要なものとは限りませんし、他にも必要なものが出てくる場合もあります。
例えば、着物と袴を買って、自分で必要なものをそろえていく人は、これから紹介するものがほとんど全部必要です。
しかし、レンタルのセットプランを選択した人の場合、業者さんによって、着付け小物、長襦袢などがセットに入っていることもあるし、入っていないこともあります。どの業者さんのどのプランを選ぶかによって、必要なものは違ってきます。

この記事を読んでどんなものが必要になりそうなのかをまずは知っておき、実際に買うのは、あなたが利用する業者さんや美容室などで必要なものを確認してからにしましょうね。
では、着物&袴を着るときに、どんなものが必要なのかをご紹介していきますね!
必要なもの① 着付け小物
着物&袴を着るには、着付け小物が必要です。
レンタルのセットプランによっては、着付け小物が含まれている場合もあります。含まれていない場合は用意する必要があります。
着付け小物といわれても、何を指しているのかピンとこない方もいるかもしれませんが……、多くの場合、以下のようなものが必要になります。
・えりしん
・腰ひも
・伊達じめ
・帯板
誰が着付けをしたとしても、上の4つは必要なのですが、着付けの方法によって他にも必要なものが出てくることがあります。ですから、着付けを誰か(レンタル業者や美容院など)にお願いする予定の人は、このほかに何が必要なのかを確認してみてくださいね。
これらの着付け小物を何も持っていない人は、一つ一つ買い集めようとしなくても大丈夫。セットになったものがネットで売っています。
家族や親せきで着物を着る人がいれば、持っている可能性が高いものばかりですので、貸してもらうという手もありそうですね。
必要なもの② 長襦袢(ながじゅばん)
着物の下に、長襦袢を着ます。着物に汗がつくのを防ぐ、着崩れを防ぐなどの役割があります。これは誰に着付けをお願いしても絶対に必要なものです。
長襦袢は、えりや袖口から見えるものですから、結構大事です。
主な素材としては、正絹(絹100%)と化学繊維(ポリエステルなど)があります。
正絹は、お値段が高いですが、肌触りも着心地もよいです。デリケートな素材であるがゆえに、家で洗濯しないでクリーニングに出した方がいいものもあります。
ポリエステルは、お値段が正絹ほど高くはなく手ごろで、家で洗濯できます。ただ、静電気が起きやすいという欠点があります。
長襦袢を選ぶときに大事なのは、着物の袖の長さに合うものを選ぶことです。袖の長さが合っていないと……例えば、長襦袢の袖が、着物の袖より短いと、長襦袢が袖から飛び出てしまったりします。
「成人式のときに長襦袢を買ったから、それを着たい」と思っている人は、着物を振袖にすれば着られます。
必要なもの③ 和装ブラジャー
着物を着るときは基本的に、素肌に和装用のブラジャーをつけ、着物用の肌着(肌襦袢とすそよけ)を着て、その上に長襦袢を着ます。
和装ブラジャーは、あったほうがいいものです。
着物を着るときには補正といって、フェイスタオルを巻いたりして着る人の体をできるだけ丸太みたいに、凸凹がないようにします。そのほうが着物がきれいに着られて、着崩れないからです。和装ブラジャーは胸の部分が凸凹になるのを抑えるような構造になっているので、これをしていたほうが美しく仕上がります。
美容院で着付けをお願いする場合、普通のブラジャーをしていると「とってください」と言われることもあるそうです。
逆に、レンタルのセットプランを利用する場合、「普通のブラジャーでOK」とする業者さんもあるようです。
誰に着付けをお願いするかで、マストになるかどうかが変わってきます。事前に確認してくださいね。
必要なもの④ 肌着
長襦袢の下には肌着を着ます。
着物用の肌着としては、これまでは「肌襦袢+すそよけ」が一般的でした。肌襦袢は上半身の下着で、汗を吸う役割があります。すそよけは下半身の下着で、歩きやすくします。
今は、「着物スリップ」や「和装スリップ」という名称で、肌襦袢とすそよけをつなげたような、ワンピースタイプのものが売っています。
レンタル業者さんによっては、上半身は肌襦袢ではなくて、衿が大きく開いている普通の肌着でOKとしている場合もあります。
必要なもの⑤ 半衿(はんえり)
半衿は、着物を着た人の衿の、肌に触れている部分です。衿の部分が白かったり、刺繍がついていたりしているのを見たことがある方もいるかもしれません。
半衿は、長襦袢の衿が汚れないようにするためのものであり、長襦袢の衿の部分に縫い付けたり、ピンでとめたりします。
長襦袢で一番汚れやすいのは衿の部分です。ファンデーションがついたりします。そのときに長襦袢全体を洗わなくても、半衿だけ取り外して洗うことができます。だから、必要なのです。
半衿は、おしゃれが楽しめる部分でもあり、いろいろな色のものが売っています。オーソドックスなのは白です。白は清潔感がありますから人気です。刺繍付きのものもあります。刺繍付きにすると、華やかな印象になります。
自分の長襦袢を着るのであれば、半衿を自分で付ける必要があります。付け方は、YouTubeにいろいろな動画がありますので、見ながらやってみてくださいね。
あるいは、着物などと一緒に長襦袢もレンタルする場合、半衿がすでについている場合もあります。
半衿にはいろいろな色、柄があって選ぶのが結構楽しいのですが、半衿を長襦袢に付ける作業を面倒だと感じる人もいると思います。そんな人は、レンタルで半衿付きの長襦袢を貸してくれるプランを選ぶといいかもしれませんね。
必要なもの⑥ 伊達衿(だてえり)
「衿」がつくものにはもうひとつ、伊達衿(だてえり)があります。これは先ほど⑤で紹介した半衿と違って、絶対に必要なわけではありません。なくても平気ですが、「あればおしゃれ度がアップする」、そういうものです。
伊達衿は、重ね衿とも呼ばれ、着物に縫い付けたり、クリップでとめたりします。そうすると、着物と長襦袢の間にもう一枚着物を着ているかのように見えて、もう一色加わることでアクセントになり、おしゃれな印象を与えます。
レンタルで、伊達衿つきの着物を貸している業者さんもあります。

半衿(はんえり)は絶対に必要ですが、伊達衿(だてえり)は「あればおしゃれ、なくても平気」ということを覚えておいてくださいね。
必要なもの⑦ 袴帯
袴を着たときに、袴の上に1~3センチほど見える帯のことで、袴帯、袴下帯、半幅帯などと呼ばれます。
袴帯は、成人式のときに使った帯とは違うものです。一般的な帯は30㎝の幅で作られていますが、袴帯は15㎝と狭いのです。
ですが、袴帯があるとおしゃれ度がアップしますし、非常に重要なアイテムです。
無地のリバーシブルタイプが一般的ですが、桜の花などの柄がついているものもあります。
大事なのは色選びです。カタログなどを見てみると袴姿のモデルさんは必ず袴帯をしていますから、参考にしてみるといいと思います。
例えば、袴帯をアクセントカラーとしてた目立たせたいときには、着物の中で小さい面積にしか使われていない色を選んでみるといいかもしれません。逆に、あまり目立たせたくないときは、着物や袴の地色の同系色にするとよさそうです。
ただし、買うときには気をつけてくださいね。浴衣用の半幅帯を買ってしまうと、ペラペラで使えない場合がありますので、袴用を買ってください。
レンタルの場合は、セットプランの中に入っていることが多いようです。
必要なもの⑧ 足袋&草履かブーツ
着物&袴を着たときの、履き物の選択肢は2つあります。それは、足袋&草履か、足首ぐらいまでのブーツか、です。
両方のメリットとデメリットを知っておきましょう。
足袋&草履が、フォーマルなスタイルです。上品な印象になります。
どちらも呉服屋さん(ネットでも、リアルでも)で売っています。
ただ、草履にはデメリットもあります。
デメリット1・雨や雪が降ると、足袋がぬれてしまう。
デメリット2・履き慣れないと、鼻緒が痛くなり、足が疲れる。
デメリット3・ブーツを履いた人と並んで立つと、背が低く見える。
これらのデメリットへの対応としては、式典のときだけ草履を履いて、移動するときはブーツに履き替える、という手もあります。
一方、ブーツのメリットは、歩きやすいことです。雨が降っても雪が降っても大丈夫。防寒対策もばっちりです。
ただ、カジュアルな印象になります。
ブーツを履くときは、中に履くタイツや靴下を用意する必要があります。

草履とブーツ、どちらも素敵です。メリットとデメリットを知ったうえで、お好きな方を選んでくださいね。
必要なもの⑨ 髪飾り
髪飾りは、ネットのアクセサリー屋さん、美容室、呉服屋、手作り品を扱うサイト、フリマアプリなどで買うことができます。
レンタルのセットプランを利用する人は、髪飾りも含まれる場合と、自分で用意する場合がありますので、確認してくださいね。
髪飾りを選ぶときのポイントは3つです。
・髪飾りは、着物と袴の色や雰囲気に合わせましょう。
・色は、着物や袴に使われている色と同じにするのが基本です。
・ヘアカタログなどを参考にして、ヘアスタイルをどうするのかを決めてから、どのぐらいの大きさの、何を飾るのかを考えましょう。
髪飾りには種類がいくつかあります。
・水引や組ひも……今どきな感じです。
・つまみ細工……かわいい雰囲気で、古典柄の着物に合います。
・大きめのリボン……大正ロマン風になります。
・アートフラワー……華やかでおしゃれな印象です。
・レース……くすんだ感じの袴に合わせると素敵です。
例えば、アートフラワーにレースと組みひもをプラスするなど、組み合わせてある商品もたくさんあります。あなたの好みに合うものを探してみてくださいね。
必要なもの➉ バッグ
着物&袴に合わせるバッグの定番は、和風の巾着です。かわいい感じになります。
それから、和装バッグを持っている人も多いようです。
これらを持っているとバッグまで、和のトータルのコーディネートが完成します。
ただし、どちらも小さめなので、あまりものが入らず、実用的ではありません。

卒業式当日は記念品をもらったりして荷物が増えるかもしれません。サブバッグを用意しておいたほうがよさそうです。
必要なもの⑪ 着物の上に着るもの
卒業式が行われるのは、3月の上~下旬ぐらいでしょうか。その頃は気温が日によって変わりやすくなります。事前に天気予報をチェックして、卒業式当日の天気と気温に合った準備をする必要があります。
例えば、最高気温が10度ぐらいで、冬に逆戻りしたような寒さになったり、雪や雨が降ったりすることもあります。その場合は、着物の上に羽織るものが必要です。
逆に、最高気温が20度ごえで、晴れて、初夏のような陽気になったら、羽織るものは特に必要ないでしょう。ただし、直前にならないと天気も気温もわからないですから、何か用意しておいたほうが安心かもしれません。

着物&袴の上に着るものとして、以下の3つのどれかを選ぶ人が多いようです。
・着物用のコート 着物の袖が入るコートです。今後も着物を着ようと思っている人は、思い切って買っておくと、冬のお出かけで活躍するかもしれません。
・ショール ショールがあれば暖かいです。成人式のときに使ったフェイクファーのショールでもOKです。
・ポンチョ ポンチョなら袖を気にしないで、着物の上から着られます。普段も着られるポンチョを用意しておくと経済的かもしれませんね。ただし、ポンチョを着ると、その上に肩からバッグをかけることができませんので、手で持つバッグを検討する必要があります。
買うときは、呉服屋さんのほか、中古の着物屋さん、フリマサイトなども見てみるといいかもしれません。
【まとめ】着物を着るのに必要なもの、基本は11点
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今回は袴を着るときに必要なもの、11点をご紹介しました。
まとめますと……。
・着物&袴をレンタルする人は、セットの内容によって準備するものが違う。
・着物を着るときの基本として、着付け小物、長襦袢、和装ブラジャー、肌着、袴帯が必要。
・半衿は絶対に必要、伊達衿はなくても平気。
・このほかに、足袋&草履かブーツ、髪飾り、バッグ、着物の上に着るものも必要。
着物って準備するものがいろいろあって、面倒くさそう……というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、まとめると↑これだけです。これらがあれば着られます。
どれも町の呉服屋さんやネットの呉服屋さんで買えます。
あなたに必要なものは何かを確認し、卒業式当日までにそろえてみてくださいね。